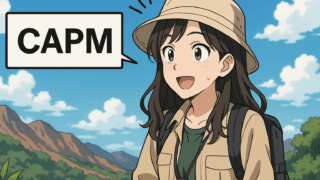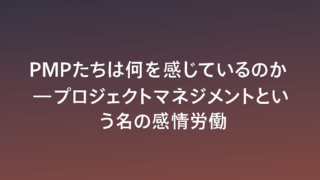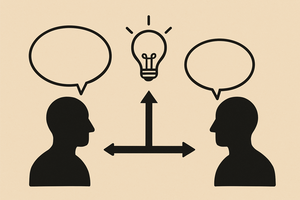野村です。
2025年4月3日に名古屋で開催したダイアローグワークショップについて、振り返りをまとめます。
どんなワークショップなの?
先日noteに書いた記事「対話をつくる側へ」——ダイアローグワークショップ実践と発展の内容をベースに実施しました。
このワークショップでは、普段なかなか体験する機会のない「ダイアローグ」を体感していただきました。
さらに今回は、以下のような多層的な体験を提供しました:
- ダイアローグに参加する
- メタ対話の立場に立つ(対話について対話する)
- 自らダイアローグをつくり出す
- そのプロセス自体をメタ対話する
ここで言うダイアローグとは?
一般的なおしゃべり(緊張もなく、気楽に話す雑談)でもなく、
何かを決定するための会議(権威や権限で一つの結論に持っていく場)でもありません。
このワークショップで扱うダイアローグとは:
- 100%、相手に意識を向ける
- 自分の感じたこと・考えたこと・気づいたことを伝える
- 合意を目指さず、対話を続ける
というものです。
参加された方へのフィードバック
説明が不足していたところがありました。
そもそもサービス開発や事業開発においてダイアローグがなぜ必要か?
たとえば、以下のような場面でダイアローグは求められます:
- アイデアの初期段階
- 顧客とのリサーチ面談
- 各種テストやプロトタイピングの場面
「インタビュー」と呼ばれることもありますが、顧客開発においては、形式的な問いかけではなく、より「面談」に近いものになります。つまり、それはダイアローグです。
100%、相手に意識を向けることで、バイアスの少ない本質的な言葉を引き出すことができます。
また、ステークホルダーやチームとの関係構築においても、ダイアローグが不可欠です。
関係性は、ダイアローグを通じて初めて「つくられる」からです。
弁証法ってなんだ?
ワーク中、「弁証法」という言葉をふと使ってしまいました。
実際、あるチームで以下のような気づきがあったのです:
「異なる意見が出ても、対話を通じてその先に進める」
ダイアローグは、一つの結論を目指さず、多様な声が共存し続ける場です。
しかしその継続のなかで、互いの意見を超える何かが立ち現れてくることがあります。
この現象こそが、弁証法的なものだと私は考えています。
以下は、その理解をChatGPTと対話しながらまとめてもらったものです:
弁証法とは、対立する意見や立場を単に優劣で決めつけるのではなく、
対話を通じて双方を吟味し、そこからより深い理解や新たな視点を導き出す思考の方法です。
古代ギリシャに起源を持ち、ヘーゲルやマルクスらによって発展しました。
基本構造は、「テーゼ(命題)」「アンチテーゼ(反命題)」「ジンテーゼ(総合)」の三段階です。対立した意見がぶつかるとき、一方を否定して終わるのではなく、両者の中にある真理を汲み取り、新しい理解へとつなげていくのが弁証法の特徴です。 この考え方は、人間関係や組織の中でも応用が可能です。たとえば「計画的に動くべき」と「柔軟に対応すべき」が対立する場合、「基本方針は立てるが、現場では柔軟に対応する」といった折衷案が生まれるかもしれません。 弁証法の本質は、「矛盾や対立は悪ではなく、理解を深めるきっかけである」と捉える姿勢です。異なる価値観のあいだを橋渡しする力として、現代社会において非常に有効な知恵だと言えるでしょう。
ChatGPT
ふりかえり(感じたこと、考えたこと、気付いたこと)
思いついたことを箇条書きで振り返ってみます。
- スライドやパワーポイントを最小限にしたが、問題はなかった
- 自己紹介(なぜ自分がここにいるのか)はやはり必要と感じた
- ロジックの説明を減らしすぎたかもしれない(バランスが難しい)
- 今回は、ダイアローグが始まるまでの時間が過去最短だった
- ダイアローグから先へ進む可能性を、実感として得られた
- 反復練習の必要性や、対立からの統合について、参加者が自ら気づいていた
- ダイアローグの反復コースを実施するなら、最初の立ち上げが鍵だと再認識した
- モノローグ傾向の強い経営幹部層には、もっと手前の働きかけが必要だと痛感した
背景と今後
3〜4年前から、「ダイアローグを立ち上げるワーク」を始めましたが、当初はうまくいかず、現在の形式になるまで試行錯誤が続きました。ちょうど今の形になって1年。今では、立ち上がりのスピードも安定し、手応えを感じています。
事前に理屈を伝えすぎないほうがうまくいく、という仮説も今回あらためて確認できました。
「モノローグの危険性を強調しすぎなくてもいい」と感じたのも、新たな気づきです。
とはいえ、冒頭の説明が少なすぎて納得感が下がった可能性は否めず、悩ましいところです。
今回特に嬉しかったのは、「メタ対話」や「自ら問いを立てる」に到達できたこと。
2時間半の中でここまでたどり着けたのは、大きな達成感があります。
最後に
以前は、「毎回テーマを変えながら毎週繰り返す」という形式でダイアローグの導入を行っていました。
しかし、参加者がダイアローグを「ファシリテート」できるようになると、「何を繰り返すか?」という設計自体を見直す必要があります。
たとえば、「ダイアローグをファシリテートしたことを、ダイアローグする場」、つまり「メタ対話ファシリテーション・ダイアローグ」が必要になるのかもしれません(ちょっと混乱しそうですが…)。
投稿者プロフィール
- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長
- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。
最新の投稿
 PMP試験対策2025年7月5日PMP試験の改訂はそろそろ?
PMP試験対策2025年7月5日PMP試験の改訂はそろそろ? CAPM試験対策2025年7月4日CAPM試験対策2025!再始動!
CAPM試験対策2025年7月4日CAPM試験対策2025!再始動! PMP試験対策2025年6月29日【後編】プロジェクトマネージャーは、怒ってもいい。
PMP試験対策2025年6月29日【後編】プロジェクトマネージャーは、怒ってもいい。 PMP試験対策2025年6月29日【前編】PMPたちは何を感じているのか――プロジェクトマネジメントという名の感情労働
PMP試験対策2025年6月29日【前編】PMPたちは何を感じているのか――プロジェクトマネジメントという名の感情労働