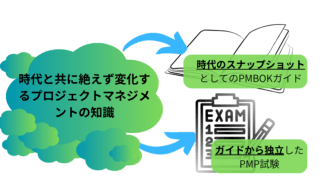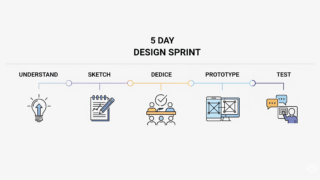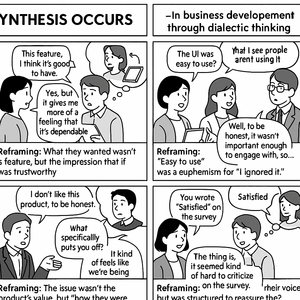──事業開発における弁証法
矛盾だらけの日々こそが、進化の種だった。
事業開発の現場は、迷いとズレとぶつかり合いの連続。
でも、その“せめぎ合い”こそが、私たちを深く考えさせ、次の一歩を導いてくれる。
この記事では、弁証法というちょっと難しそうな考え方が、意外にも実務に根ざしていることを、現場視点で綴ります。
「弁証法」と聞くと、少し哲学的で、抽象的な世界を思い浮かべる人が多いかもしれません。あるいは「難しそう」「うちの現場には関係ない」と思われるかもしれません。
私は思うのです。
弁証法は、現場にすでに生きている。
なぜなら、事業開発の最前線では、日々、無数の「対立」や「矛盾」が生じているからです。たとえば──
- プロトタイプを喜んでほしい vs. プロトタイプを率直に批判してほしい
- ユーザーが「いいですね」と言った vs. 本心ではなく社交辞令かもしれない
- 上司の意見も取り入れたい vs. 顧客の評価こそが全てだ
- 顧客の声を尊重したい vs. 自分たちのビジョンを貫きたい
- 早くリリースしたい vs. 品質を妥協したくない
- チームをまとめたい vs. 多様な視点を尊重したい
- データに基づいて判断したい vs. 直感や現場感覚を信じたい
- 綿密に計画したい vs. 柔軟に対応したい
- すぐに結果を出したい vs. 長期的な価値を大切にしたい
- リスクを取って挑戦したい vs. 失敗を避けて安定を求めたい
- 顧客の要望に応えたい vs. プロダクトの方向性を守りたい
- スピードを上げたい vs. チームのコンディションを優先したい
- 自由な発想を歓迎したい vs. フレームワークに沿って進めたい
こうした“せめぎ合い”の中で、プロダクトは育っていきます。
これらはすべて、弁証法的な状況です。現場はいつも「テーゼ(主張)」と「アンチテーゼ(反対意見)」の間で揺れ動きながら、葛藤し、模索しています。
そしてその中から、「ジンテーゼ(統合された新たな視点)」が、ふと、訪れる瞬間がある。
ここで大切にしたい前提があります。世界は、直線的に進歩しているのではなく、運動し、変化し、時に揺れ戻りながら、進化していくものだということです。対話や葛藤は、その運動のひとつなのです。
「問い」がなければ、気づきは生まれない
私はこれまで、事業開発やプロダクト開発に関わる多くの現場で、ファシリテーターや伴走支援の役割を担ってきました。
その中で確信しているのは、人と人との間に「対話」がなければ、深い気づきは生まれないということです。
たとえばプロトタイプを使った面談でも、ただ感想を聞くだけでは本質に届きません。違和感を見つけ、そのズレに対して「なぜそう感じたんですか?」と掘り下げる。そのとき初めて、ユーザーの本当のニーズが立ち現れてくるのです。
弁証法とは、こうした「問い直し」の姿勢そのものなのだと、私は思います。
弁証法はスキルではなく、姿勢である
「弁証法なんて、難しい」「哲学なんでしょ?」そう言われることもあります。
でも、弁証法的な姿勢は、特別なスキルではありません。むしろ、日常的に私たちが直面する“迷い”や“ズレ”に、どう向き合うかという、とても実践的な態度です。
- チームの中で意見が食い違ったとき、すぐに多数決にするのではなく、立ち止まって考える
- ユーザーの声がプロダクトの意図とズレていたとき、どちらが正しいかを決める前に、その“ズレ”に意味があると考える
こうした営みこそが、事業開発における“思考の深さ”を生み出す源泉になるのです。
さらに大切なのは、常にアンチテーゼを探す姿勢です。
現場では、無意識にテーゼ(ひとつの見方・方向性)に偏りがちです。議論が滑らかすぎるときこそ、「逆の視点はないか?」「反対意見は本当にないのか?」と自らに問いかける必要があります。
アンチテーゼは、チームを混乱させるためにあるのではなく、新たなジンテーゼを導くための大切な材料なのです。
私自身の言葉で言うなら、事業開発は、常に“ヒリヒリ感”を味わう営みだと思います。うまくいっているように見えても、どこかに小さなズレや違和感があり、それに敏感であること。そのヒリヒリ感こそが、アンチテーゼを取り込んでいる証なのかもしれません。
弁証法を実装するために──私がしていること
私は、実務で「弁証法を使え」とは言いません。言葉で教えても、実感が伴わなければ意味がないからです。私が現場で使うのは、「反対の見方をしてみよう」という問いかけです。
だからまず、問いを投げかけます。
「今、どんなことを感じましたか?」 「少し違和感があったかもしれません。その違和感、もう少し言葉にできますか?」
こうして、参加者自身の中にある“矛盾”や“未整理のもの”を丁寧にすくい上げ、少しずつ場に出していく。
そして、それらを「ぶつけ合う」のではなく、「響かせ合う」ような対話の場をつくります。
弁証法は、方法論ではなく、文化です。関係性の中で育てていくしかありません。
だからこそ私は、問いを立て、対話をつくる。その繰り返しを、大切にしています。
最後に
「矛盾を抱える」ことは、不安です。葛藤はしんどいです。
でも、そこから目をそらさず、少しだけ立ち止まり、問いを立ててみる。
そして、人と対話してみる。
その営みの中にしか、本当に新しいプロダクトも、事業も、望ましい関係も、生まれないのではないか──
私は、そう考えています。
とはいえ、やはり、弁証法そのものを理解することも必要なのではないか、と最近感じています。次回のトレーニングからは、弁証法の考え方そのものも、もう少し丁寧に紹介してみようと思っています。
──こういう姿勢そのものが、まさに弁証法的アプローチなのかもしれませんね。
投稿者プロフィール
- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長
- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。
最新の投稿
 CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!
CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの
ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint
事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?
ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?